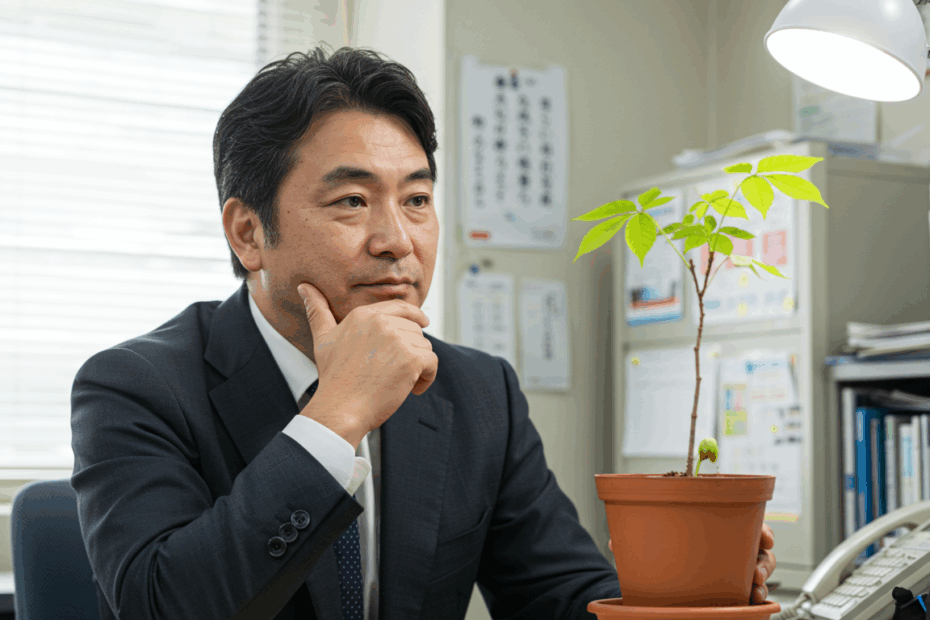記事の監修

代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト
「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭
株会会社村上経営研究所
代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト
「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭
経営コンサルタントとして26年以上、人材育成・組織開発・経営者支援に携わる。建築士としての構造思考と感情・行動の知見を融合し、「人と企業の生かせいのち」を軸に、本質的な意思決定と持続的な組織成長を支援している。
「一生懸命、教えているつもりなのに…」
「どうしてウチの社員は育ってくれないんだ…」
スマートフォンの画面を見ながら、ため息をついている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
手塩にかけて採用し、期待を込めて現場に送り出した社員が、思うように成長してくれない。
それどころか、数年で辞めてしまう。その繰り返しに、心を痛めていませんか?
その悩み、決してあなた一人のものではありません。
多くの中小企業が、同じ壁にぶつかっています。
しかし、その根本原因は、社員の意欲や能力、あるいは現場の指導力だけの問題ではないのです。
多くの場合、企業の未来を見据えた、戦略的な「人材育成計画」が描けていないことにあります。
この記事では、そんな「人が育たない」という根深い悩みを解決するため、明日から実践できる人材育成計画の具体的な立て方を5つのステップで徹底解説します。
単なる研修リストの作成ではありません。
会社の羅針盤である経営戦略と連動させ、社員一人ひとりの成長が会社の成長に直結する。
そんな「勝てる組織」の設計図を一緒に描いていきましょう。

なぜ今、中小企業に「戦略的な人材育成」が必須なのか?
「目の前の業務で手一杯で、育成まで手が回らない」という声も聞こえてきそうです。
しかし、もはや人材育成は「余裕があればやること」ではありません。
会社の存続をかけた最重要の経営課題です。
技術革新と人材不足。待ったなしの外部環境
現代のビジネス環境は、凄まじいスピードで変化しています。
AIやDXといった技術革新の波は、もはや大企業だけのものではありません。
チャットGPTのような生成AIをいかに業務に取り入れるか、RPAでいかに定型業務を自動化するか。
こうした変化に対応できなければ、生産性の差は開く一方です。
さらに、少子高齢化による深刻な人手不足は、中小企業にとって死活問題です。
限られた人材で高いパフォーマンスを出すことはもちろん、優秀な人材に「この会社で働き続けたい」と思ってもらえなければ、競争の土俵にすら立てません。
新しいスキルを学び続け、変化に対応できる人材を計画的に育てていくこと。
これこそが、荒波を乗り越えるための唯一の羅針盤となります。
「成長・定着・継承」このサイクルが競争力の源泉
戦略的な人材育成計画は、単に社員を育てるだけでなく、会社に3つの大きな果実をもたらします。
- 成長の実感と定着人は「成長している」と実感できる場所に、留まりたいと思うものです。会社が明確なキャリアパスを示し、成長の機会を提供することで、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)は飛躍的に高まります。結果として離職率が下がり、採用コストの削減にも繋がるのです。
- 組織力の向上計画的な育成は、個人のスキルアップに留まりません。OJTや勉強会を通じて、知識やノウハウが組織全体で共有され、いわゆる「属人化」を防ぎます。誰かが辞めても業務が滞らない、強い組織の土台が築かれます。
- 未来への事業継承経営者の皆様にとって、事業継承は避けて通れない道です。経営理念や、長年培ってきた独自の技術・ノウハウを次の世代にどう繋いでいくか。日々の業務を通じて、計画的に後継者や次世代リーダーを育成していくことが、会社の未来を確かなものにします。
この「成長・定着・継承」という好循環を生み出すエンジンこそが、戦略的な人材育成計画なのです。
そもそも「人材育成計画」とは何か?
「人材育成計画なら、ウチにもあるよ」という方もいるかもしれません。
しかし、それが単なる「研修参加リスト」や「資格取得目標リスト」になっていないでしょうか。
「育成の設計図」という本当の意味
本当の意味での人材育成計画とは、「会社の経営目標を達成するために、どんな人材が、いつまでに、どうやって必要なスキルを身につけるかを定めた、育成の全体設計図」です。
家を建てる時、いきなりレンガを積み始める人はいません。
必ず、どんな家を建てたいかという「完成予想図」と、そのための「設計図」があるはずです。
人材育成も全く同じです。
「研修をやること」が目的になってしまうと、せっかくの時間とコストを投じても、現場の行動は何も変わらない、という最悪の結果を招きます。
育成は手段であり、目的はあくまで経営目標の達成である。この大原則を決して忘れてはなりません。
経営戦略から逆算して初めて意味を持つ
効果的な人材育成計画は、必ず経営戦略という羅針盤と連動しています。
- 経営戦略:「3年後にECサイトの売上を倍増させる」
- →必要な人材:Webマーケティングの知識を持ち、データ分析から改善提案ができる人材。SNS運用の専門スキルを持つ人材。
- →育成計画:Webマーケティング研修への参加、データ分析ツールの習得、OJTでの実践。
- 経営戦略:「顧客満足度で地域No.1になる」
- →必要な人材:高いコミュニケーション能力で顧客の潜在ニーズを引き出せる人材。クレーム対応を組織の改善に繋げられるリーダー。
- →育成計画:傾聴力や提案力を高めるロールプレイング研修、クレーム対応研修、マネジメント層へのコーチング研修。
このように、会社の進むべき未来から逆算して「あるべき人材像」を定義すること。これが、成果に繋がる人材育成計画の絶対的な出発点です。
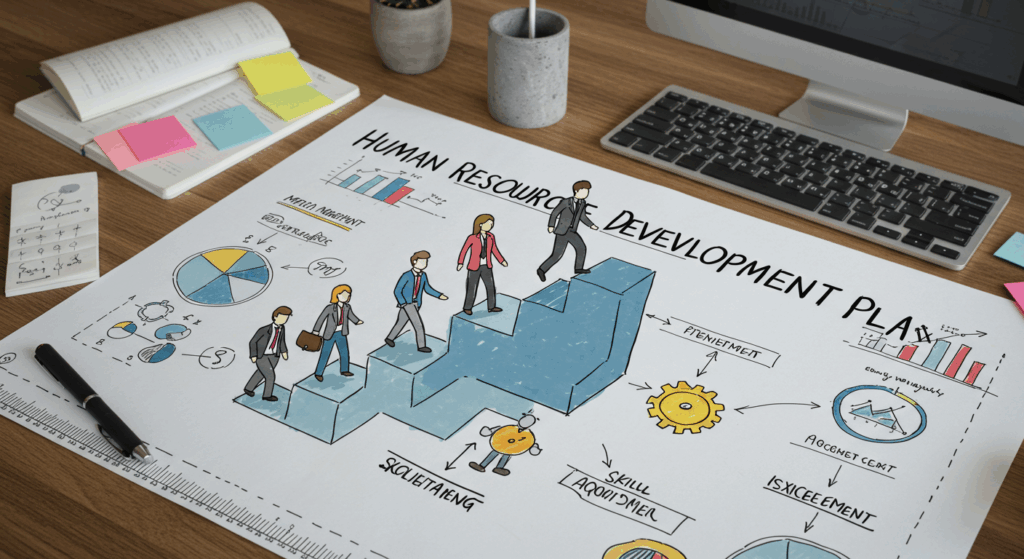
【5ステップで実践】人材育成計画の立て方
ここからは、いよいよ具体的な計画の立て方を、経営者視点で押さえるべき5つのステップに沿って解説します。
ステップ1:経営課題と将来像から「理想の人材」を描く
最初のステップは、未来から現在を見ることです。
まず、経営者自身が「3年後、5年後、会社をどんな姿にしたいか」というビジョンを具体的に描きます。そして、そのビジョン達成のために「今、解決すべき経営課題は何か」を明確に言語化しましょう。
- 「新規顧客の開拓が滞っている」
- 「若手社員の定着率が低い」
- 「部門間の連携が悪く、生産性が上がらない」
課題が明確になったら、それを解決できる「理想の人材像(ペルソナ)」を、役職や階層ごとに具体的に描きます。
【ペルソナ設定の例:営業マネージャー】
- 役割:3名の部下を持つプレイングマネージャー
- スキル:
- 自身の営業目標達成はもちろん、チーム全体の予実管理ができる。
- CRMのデータを分析し、科学的なアプローチで営業戦略を立案できる。
- 部下一人ひとりの特性に合わせたコーチングを行い、成長を支援できる。
- マインド:
- 会社の理念に共感し、自らの言葉で部下に語ることができる。
- 失敗を恐れず、新しい営業手法にチャレンジする姿勢を持つ。
この「理想の人材像」が、育成のゴール、つまり北極星となります。
ステップ2:現状把握と「ギャップ」の明確化
次に、その理想に対して、今の社員たちがどの位置にいるのかを客観的に把握します。
- スキルマップの作成:社員一人ひとりが持つスキルを一覧で可視化する。
- 面談・アンケート:上司や本人との面談、あるいは無記名アンケートで意識や課題感を把握する。
- 360度評価:上司・同僚・部下など、多角的な視点から評価する(簡易的なものでもOK)。
ここで最も重要なのは、「理想」と「現状」の間に横たわるギャップ(課題)を具体的に特定することです。
「コミュニケーション能力が低い」という漠然とした課題ではなく、「お客様の本当の課題を引き出すためのヒアリング力が不足している」「会議で論理的に話す力が弱い」というレベルまで、解像度を高くして課題を洗い出しましょう。
ステップ3:育成目標の設定と「スキル」の整理
ギャップが明確になったら、それを埋めるための具体的な育成目標を設定します。この時、SMARTというフレームワークを意識すると、目標がより具体的になります。
【SMARTな目標設定の例】
- S (Specific):具体的か? → 営業部のAさんが
- M (Measurable):測定可能か? → 担当するB社に対して
- A (Achievable):達成可能か? → 上司のサポートを受けながら
- R (Relevant):経営目標に関連しているか? → 新規サービス(高単価商品)の
- T (Time-bound):期限があるか? → 3ヶ月以内に、単独で提案できるようになる
目標が決まったら、それを達成するために必要なスキルを**「知識・技術・意識(KSA)」**の3つの観点で整理すると、育成すべきことがよりクリアになります。
ステップ4:育成手段の選定と「計画」への落とし込み
いよいよ、具体的な育成方法を選んでいきます。
育成手法は、大きく分けて3つあります。それぞれの特性を理解し、戦略的に組み合わせることが重要です。
- OJT (On-the-Job Training)
- 内容:実際の業務を通じた指導、先輩との同行、1on1ミーティングなど。
- 特徴:最も実践的で、コストも抑えられる。ただし、指導者のスキルに成果が左右されやすく、場当たり的になりがち。計画的なOJT(目的やゴールを明確にした指導)が不可欠。
- Off-JT (Off-the-Job Training)
- 内容:外部研修、セミナー、eラーニング、社内勉強会など。
- 特徴:体系的な知識や専門スキルを効率的に学べる。ただし、コストがかかることや、学んだ内容が実践に繋がりにくい場合がある。
- 自己啓発支援 (SDS: Self-Development System)
- 内容:資格取得の費用補助、書籍購入制度、通信教育の斡旋など。
- 特徴:社員の自発的な学びを促進し、学習意欲の高い社員の満足度を高める。
これらの手法を、対象者のレベルや習得スキルに応じて効果的に組み合わせ、年間・半期・月間といった時間軸に落とし込んだ、具体的な年間育成計画表を作成します。
ステップ5:実行・評価・改善の「PDCAサイクル」を回す
計画は、作って終わりでは1ミリも意味がありません。
最も重要なのは、このサイクルを粘り強く回し続けることです。
- Plan(計画):ステップ4までで作成した計画。
- Do(実行):計画に沿って、OJTや研修を実行する。
- Check(評価):
- 本当にスキルは身についたか?(理解度テスト、レポート提出)
- 現場での行動は変わったか?(上司や同僚からのヒアリング)
- 業績や組織に良い影響はあったか?(売上、生産性、顧客満足度など)
- Action(改善):
- 評価の結果を踏まえ、計画を見直す。「研修内容が難しすぎた」「OJTの指導者が忙しすぎて機能していない」など、原因を分析し、次の計画に活かす。
このPDCAサイクルを地道に回し続けること。
それこそが、人材育成計画を「絵に描いた餅」で終わらせないための唯一の方法です。

【階層別】人材育成計画で押さえるべきポイント
育成は、相手の立場や役割によってアプローチが異なります。
ここでは各階層で特に重視すべき育成のポイントを解説します。
若手・中堅社員:プロとしての土台作り
この層のゴールは「一人前の戦力として自立すること」です。
報告・連絡・相談といった基本動作の徹底に加え、担当業務を確実に遂行する専門スキルを習得させます。
「給料をもらうプロである」という当事者意識を醸成することが重要です。
管理者層(課長・部長):チームで勝つ力の強化
プレイングマネージャーから脱却し、「チームの成果を最大化する」ことがミッションです。
問題解決力やマネジメント能力はもちろん、部下のやる気を引き出し、成長を支援するコーチング力やフィードバック力を重点的に強化します。
幹部層:経営者の右腕となる力の習得
経営者と同じ視座で事業を動かす力が求められます。
会社の理念やビジョンを自分の言葉で語り、組織に浸透させる「理念浸透力」、そしてゼロから事業を生み出す「企画構想力」が不可欠です。
経営層:未来を創る力と人間力の深化
経営者自身も学び続ける存在です。
目先の業績だけでなく、社会の変化を読み解き、会社の未来を描く「未来構想力」。
そして、社員や顧客を幸せにするために、人間とは何かを深く洞察する「人間観」を磨き続けることが、最高の育成環境となります。
人材育成計画を「現場で機能させる」組織づくり
精緻な計画も、実行する組織の土台がなければ根付きません。
計画倒れを防ぐための3つの秘訣をお伝えします。
- 人事任せはNG。経営者が「本気」の旗を振る中小企業において、育成の成否は経営者の本気度で9割決まります。
育成を現場任せにせず、経営者自らが「人材育成こそ最重要の経営課題だ」というメッセージを発信し続けること。研修の冒頭で社長が想いを語る、それだけでも現場の空気は一変します。 - 「学習する組織文化」を根付かせる挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、その挑戦から得られた学びを称賛し、組織の資産として共有する。
このような心理的安全性の高い風土が、「学習する組織」の土台となります。まずは「ありがとう」と「ナイスチャレンジ!」が飛び交う職場を目指しましょう。 - 成長を「見える化」し、フィードバックを続ける育成の成果はすぐには見えにくいものです。
だからこそ、意識して「見える化」することが重要です。
資格取得や後輩指導といった行動を評価制度に組み込んだり、改善事例の発表会を開いたりするのも良いでしょう。
そして、1on1などを通じて定期的にフィードバックを行い、社員の成長を認め、次への期待を伝えることが、モチベーションの火を灯し続けます。

人材育成・組織改革なら「村上経営研究所」へ
ここまで、中小企業における人材育成計画の重要性と、その具体的な立て方について解説してきました。
「重要性は痛いほどわかった。でも、自社の課題と結びつけて、具体的な計画に落とし込むのは、やはり一人では難しい…」
「計画を立てても、結局PDCAが回らずに形骸化してしまいそうだ…」
もし、今あなたがそう感じているなら、それは当然のことです。企業の未来を左右する人材育成は、片手間でできるほど簡単なものではありません。
そんな時こそ、私たち「村上経営研究所」のような、組織課題と向き合ってきた専門家の力を頼ってください。
私たちは、単に綺麗な計画書を作るコンサルタントではありません。経営者の皆様と膝を突き合わせ、貴社の経営戦略と深く連動した、本当に現場で機能する「生きた育成の仕組み」を一緒に創り上げます。
【LINE登録者様 限定】
今すぐ、あなたの会社の「人が育つ」仕組み作りを始めませんか?
村上経営研究所のLINE公式アカウントにご登録いただいた方には以下の無料プレゼントがあります。
- 管理職育成を阻む“3つの壁”チェックシート
- 社員が辞めない会社の社長がやっている5つのこと
さらに、ご希望の方には、経験豊富なコンサルタントが貴社の課題を直接ヒアリングし、解決の方向性をアドバイスする【30分無料オンライン相談】も実施中です。
相談したからといって、無理な営業は一切いたしません。
まずは貴社の悩みをお聞かせいただくことから、すべてが始まります。
この小さな一歩が、貴社の「人が育ち、組織が強くなる」未来への、大きな一歩となることをお約束します。