記事の監修

代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト
「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭
株会会社村上経営研究所
代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト
「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭
経営コンサルタントとして26年以上、人材育成・組織開発・経営者支援に携わる。建築士としての構造思考と感情・行動の知見を融合し、「人と企業の生かせいのち」を軸に、本質的な意思決定と持続的な組織成長を支援している。
はじめに
「社員のために研修を実施し、OJTで丁寧に指導しているはずなのに、なぜか期待通りに育ってくれない…」
「育成が現場任せ・個人任せになっており、教える人によって指導内容がバラバラ。結果として、組織全体のレベルが上がらない」
中小企業の経営者様から、このような人材育成に関する切実な悩みを伺うことが少なくありません。
時間とコストをかけているにもかかわらず、成長が見えにくい。その最大の原因は、育成の根幹となる「目標設定の曖昧さ」にあるかもしれません。
明確なゴールがないままでは、社員は何をどのレベルまで目指せば良いのか分からず、指導する側も感覚的・属人的な指導に終始してしまいます。
結果として、育成は形骸化し、社員のモチベーションも組織の成長も停滞してしまうのです。
本記事では、こうした課題を解決するために、人材育成の成功の鍵を握る「目標設定」に焦点を当てます。
- なぜ、育成に「目標」が必要不可欠なのか
- 社員の能力を最大限に引き出す、効果的な目標の立て方
- 新人から幹部まで、階層別に求められる目標の違い
- 目標を絵に描いた餅で終わらせない、組織全体で運用する仕組みづくり
など、人材育成における目標設定の考え方から具体的な実践方法までを体系的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、貴社の人材育成を「感覚的な指導」から「戦略的な投資」へと転換させ、社員一人ひとりが自律的に成長し、組織全体の成果に貢献する未来への第一歩を踏み出すことができるはずです。
中小企業の人材育成における「目標設定」の基本と戦略的アプローチ
人材育成がうまくいかないのは「目標」の立て方に課題があるから
多くの経営者が「人は財産だ」と考え、育成に力を注いでいます。
しかし、その想いとは裏腹に、現場では成長が実感できないという壁に突き当たります。
その根本原因は、育成の「設計図」である目標設定に潜んでいることがほとんどです。
人は育てているのに「育たない」現場の共通点とは
育成が機能不全に陥っている現場には、驚くほど共通した特徴が見られます。
それは、育成が「仕組み」ではなく「個人の頑張り」に依存している状態です。
- 漠然としたゴール
「早く一人前になってほしい」という期待はあるが、「何が、どのレベルでできれば一人前なのか」という具体的な基準が共有されていない。 - 場当たり的な指導
体系的な育成計画がなく、目の前の業務を教えるOJTの繰り返しに終始している。 - 評価基準の曖昧さ
成長を測る客観的な「ものさし」がないため、フィードバックが指導者の主観になりがちで、部下の納得感を得られない。 - 「背中を見て育て」の文化
育成ノウハウが個人の中に留まり、組織の資産として蓄積・共有されていない。
これらの状態はすべて、出発点となる「育成目標」が明確に定められていないことに起因します。
目的地が曖昧なままでは、どれだけ熱心に指導しても、その努力は分散し、成果には結びつきにくいのです。
明確な育成目標がないと、指導が属人的になる
育成における目標がない、あるいは曖昧であることの最大の弊害は、指導の「属人化」です。これは、教える人によって指導内容や品質がバラバラになってしまう現象を指します。
例えば、ある上司は「スピード重視」を説き、別の上司は「丁寧さが第一」と教える。
どちらも正しいかもしれませんが、教わる側は混乱し、組織として一貫した品質基準を保つことができません。
さらに深刻なのは、その優秀な指導者が異動や退職をした途端、育成ノウハウが途絶えてしまうことです。
これでは、持続的な組織成長は望めません。
育成目標とは、いわば「組織としての人材育成における共通言語」です。
この共通言語があって初めて、誰が指導しても一定の質が担保され、育成は個人のスキルから組織の力へと昇華されるのです。
なぜ「人材育成における目標設定」が重要なのか?
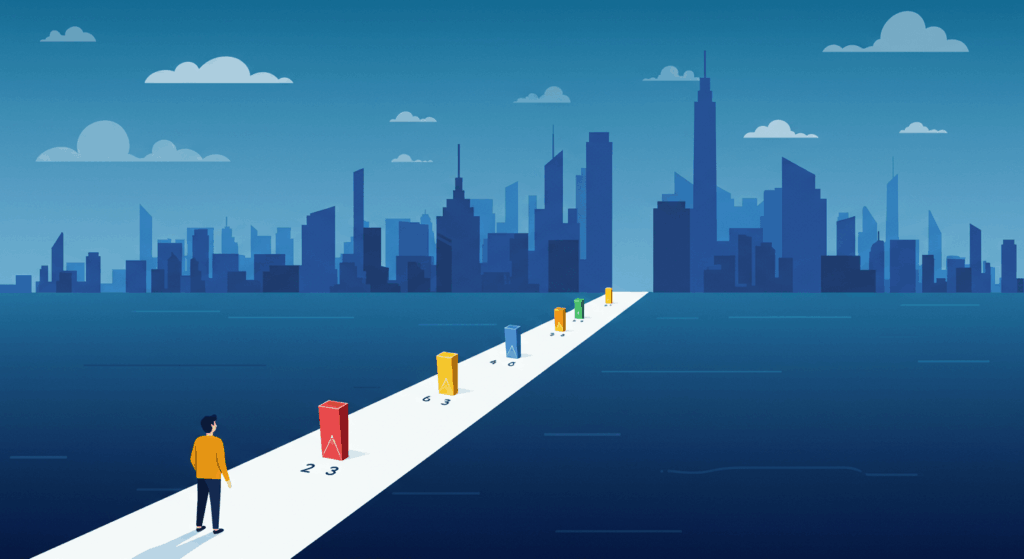
では、なぜ目標設定はこれほどまでに人材育成の成否を分けるのでしょうか。
それは、目標が持つ2つの重要な機能に答えがあります。
組織の方向性と個人の成長をつなぐ「橋渡し」になる
社員は誰しも、自分の仕事が会社の役に立っていると実感したいものです。
目標は、その実感を生み出すための重要な「橋渡し」の役割を担います。
会社の経営目標という大きな目的を、部の目標、課の目標、そして個人の目標へと具体的に落とし込んでいく。
このプロセスを通じて、社員は自分の日々の業務が、会社のどの歯車を動かしているのかを明確に理解できます。
「自分のこの努力が、会社の成長に直結している」
この感覚は、社員の当事者意識を育み、仕事へのエンゲージメントを飛躍的に高めます。
目標設定は、組織と個人を同じベクトルに向かせるための、最も強力なコミュニケーションツールなのです。
育成の成果が「見える化」される
人材育成におけるもう一つの課題は、「成長が実感しにくい」ことです。目標設定は、この課題を解決し、育成の成果を「見える化」する機能を持っています。
例えば、「3ヶ月後までに、顧客への基本提案を一人で完結できるようになる」という目標があれば、達成できたかどうかが客観的に判断できます。
- 本人にとって: 達成感を得られ、自信につながる。次のステップへの意欲が湧く。
- 上司にとって: 成長度合いを正確に把握でき、的確なフィードバックと次の課題設定が可能になる。
目標は、成長の道のりを照らす「ロードマップ」であり、進捗を確認するための「計器」です。
成果が見えることで、育成は計画的かつ効果的に進み、組織全体のモチベーション向上にも繋がります。
人材育成における目標設定の考え方と基本ステップ
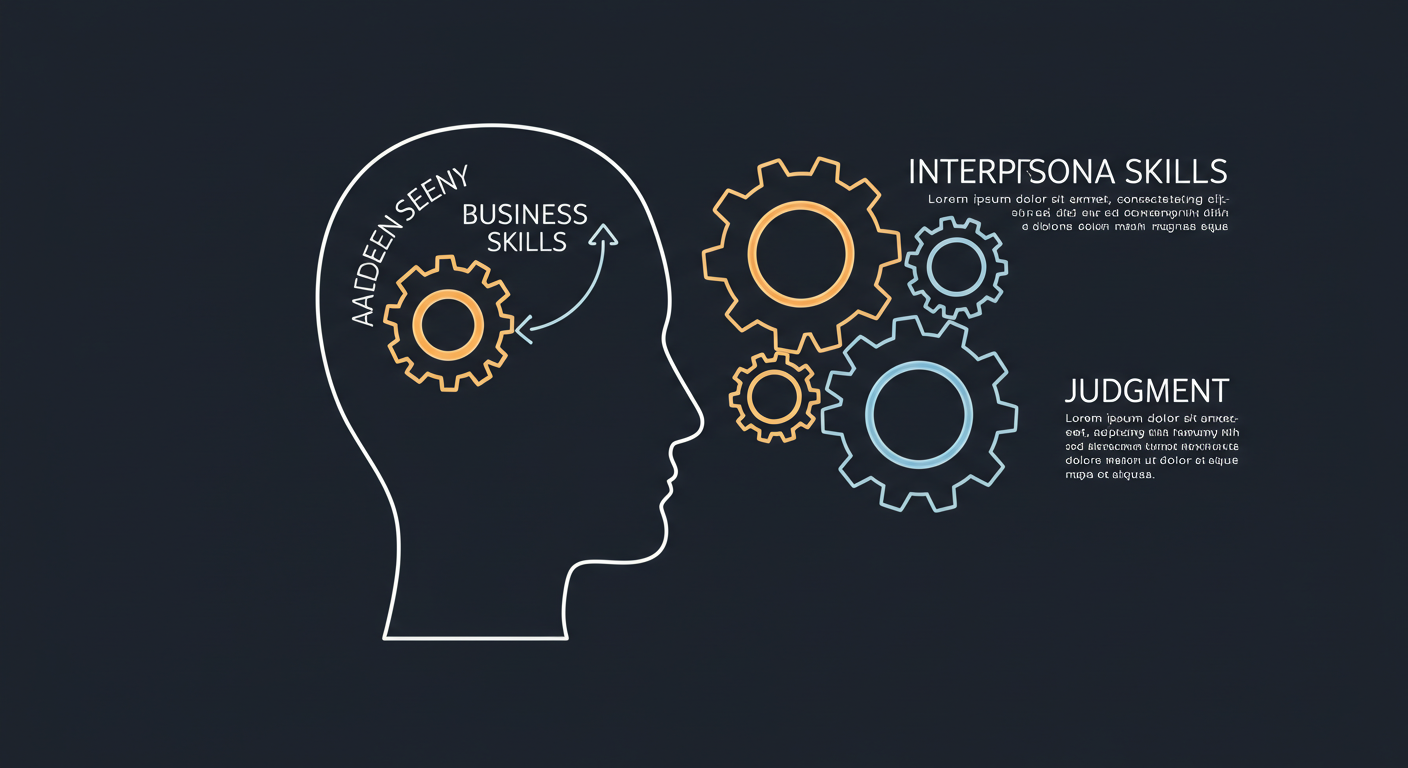
それでは、具体的にどのように目標を立てれば良いのでしょうか。
ここでは、社員の能力を多角的に捉え、その成長を段階的に促すための基本的な考え方を紹介します。
スキルの種類別に目標を立てる|業務力・人間力・判断力
人の能力は、単一のスキルだけでは測れません。
バランスの取れた人材を育成するため、以下の3つのスキル軸で目標を設定することが有効です。
- 業務力(テクニカルスキル): 業務遂行に必要な専門知識や技術。
- 目標例: 「〇〇の資格を取得する」「新システムの基本操作を1ヶ月でマスターする」
- 人間力(ヒューマンスキル): 円滑な対人関係を築き、チームで成果を出す力。
- 目標例: 「チーム会議で月1回、業務改善に関する意見を必ず発言する」「顧客からの問い合わせに対し、一次対応を完結できるようになる」
- 判断力(コンセプチュアルスキル): 物事の本質を見抜き、全体最適を考える力。
- 目標例: 「担当業務の課題を3つ挙げ、その解決策を上司に提案する」「競合他社の動向を分析し、自社の強みを活かす施策を立案する」
これら3つのスキルは、車のタイヤのようなものです。
どれか一つが欠けても、組織という車は真っ直ぐには進めません。
それぞれの階層や職種に応じて、これらのスキルをバランス良く伸ばす目標設定を心がけましょう。
知識とスキルにとどまらず、価値観と判断力を育てる
真の人材育成は、単に「知識」を教え込むだけでは完結しません。
その知識を実践で使える「見識」に、さらには困難な状況でも信念を持って決断できる「胆識」へと昇華させていくプロセスが重要です。
- 知識: 知っている状態。
(例:マーケティングのフレームワークを学んだ) - 見識: 知識と経験を結びつけ、本質を理解している状態。
(例:フレームワークを自社に当てはめ、成功要因を分析できる) - 胆識: 覚悟と責任を持って、意思決定・実行できる状態。
(例:分析に基づき、リスクを取ってでも新しい施策の実行を決断する)
目標設定においても、「〇〇を学ぶ」という知識レベルの目標だけでなく、「学んだ知識を使って△△を提案する(見識)」「提案した企画を責任者としてやり遂げる(胆識)」といった、より高い次元の思考と行動を促す目標を取り入れることで、将来の組織を担うリーダーを育てることができるのです。
階層別の目標例と育成ステップ

企業で働く人材に求められる役割は、その階層によって大きく異なります。しかし、多くの経営者や管理職が気づいていないのは、それぞれの階層で向き合うべき「育成の本質」が異なるという事実です。
新人〜管理職:問題処理から解決へのスキル育成と「育てる覚悟」
この階層では、「与えられた仕事をこなす力」から「自ら課題を解決する力」への移行がテーマです。しかし、その裏で問われているのは、管理職自身が「部下を育てること」を自らの最重要ミッションとして捉え、その成果に責任を持つ覚悟があるかです。
- 新人・若手: まずは「型」を身につける段階。
- 目標例: 「指導を受けずに定型業務を一人で完結できる」「報告・連絡・相談を適切なタイミングで実行できる」
- 中堅社員:「型」を応用し、改善する段階。
- 目標例: 「担当業務の非効率な点を改善する提案を行う」「後輩へのOJT指導を計画的に実施する」
- 管理職:部下の成長を自らの評価と直結させ、チームの成果を最大化する段階。
- 目標例: 「部下一人ひとりの成長課題を把握し、育成プランを作成・実行する」「部下の成長を通じて、チーム全体の生産性を前年比10%向上させる」
管理職にとって育成は「善行」ではありません。
自身の評価と報酬に直結する、極めて重要な「投資活動」であるという認識の転換が求められます。
幹部〜経営者層:「任せられる判断力」を育むための『修羅場』の設計
組織の未来を担う幹部層に求めるのは、優秀なプレイヤーとしての能力ではありません。
経営者が明日倒れても会社を任せられる、「経営者と同じ視座」で物事を考え、苦しい決断を下せる「胆識」です。
この領域の能力は、研修では決して身につきません。
経営者が本当に向き合うべき課題は、意図的に設計された、質の高い失敗ができる『修羅場』を経験させることです。
- 幹部候補(部長クラス): 事業・部門の未来を創る『小さな経営者』としての経験を積む段階。
- 目標例: 「担当部門の中期事業計画を策定し、その達成に全責任を負う」「失敗のリスクがある新規プロジェクトの責任者となり、撤退基準も含めて意思決定を行う」
- 経営層(役員クラス):会社全体の未来を創る段階。
- 目標例: 「全社横断の新規事業プロジェクトを立ち上げ、軌道に乗せる」「企業の持続的成長のための組織改革プランを策定し、実行を主導する」
幹部育成における目標設定とは、スキルリストの作成ではなく、「どの『修羅場』を、いつ、誰に経験させるか」という極めて戦略的な経営判断そのものなのです。
人材育成の目標を組織全体で達成する仕組みづくり
個人の目標を設定するだけでは、育成は成功しません。
しかし、多くの人事が陥る罠は、「完璧な制度」を作ろうとすることです。
本当に重要なのは、制度という「器」ではなく、その中で交わされる「中身」、つまり現場の泥臭い対話です。
目標管理(MBO)とスキルマップの活用法
目標管理制度やスキルマップは、あくまで「本音の対話」を生み出すためのきっかけに過ぎません。
- 目標管理制度(MBO)
これを単なる「評価のためのツール」ではなく「成長支援のためのコミュニケーションツール」として位置づけることが全てです。目標設定面談の場で「なぜ挑戦的な目標が出てこないのか?」といった問いを通じて、組織の隠れた課題(失敗を恐れる文化など)を炙り出す「健康診断」の機会と捉えるべきです。 - スキルマップ
個人の強み・弱みを客観的に把握し、次の育成目標を具体的に設定するための共通認識を持つことができます。また、組織全体のスキル保有状況も明確になり、戦略的な人材配置や採用計画にも活用できます。
学びと対話が根づくチームの育成
最高の育成環境は、「お互いに学び合い、高め合う文化」が根付いているチームです。人事や経営者の役割は、「制度の番人」になることではなく、現場の対話を活性化させる「触媒」になることです。
例えば、チーム内で定期的に「成功事例」だけでなく「失敗事例」を共有する場を設けることは非常に有効です。
失敗を責めるのではなく、「その経験から何を学んだか」「チームとしてどうすれば次に活かせるか」を対話する。
このような心理的安全性の高い環境が、社員の挑戦を促し、個人の経験を組織の知恵へと変えていきます。
育成を一部の管理職や人事部に任せるのではなく、チーム全員が「育てる側」であり「育てられる側」であるという意識を共有することが、持続的に成長する組織の土台となるのです。
目標達成に必要な「個人のやる気」と「組織の支援」の関係
どんなに優れた目標や仕組みも、本人の「やりたい」「成長したい」という内なる炎がなければ機能しません。
組織の役割は、その炎に薪をくべ、燃え上がらせるための「支援」にあります。
やる気・本気を引き出す仕組みとは
人のモチベーションは、「やらされ感」の中では決して高まりません。
社員が自らの意志で目標に向かう「やる気」を引き出すためには、以下の3つの要素が鍵となります。
- 自己決定感(裁量)
「目標は与えられたが、その達成方法は君に任せる」というように、プロセスにおける裁量権を与えることで、仕事への当事者意識が生まれます。 - 有能感(成長実感)
少し背伸びした「ストレッチ目標」を乗り越える経験や、上司からの具体的な承認・フィードバックを通じて、「自分は成長できている」という感覚を持つことができます。 - 貢献実感(目的意識)
自分の仕事がチームや顧客、そして会社の役に立っていると感じられること。目標が組織の方向性と連動しているのは、このためです。
経営者や管理職は、「管理(Control)」する者から、社員の成長を後押しする「支援(Support)」者へと役割意識を変える必要があります。
個人の強みを活かし組織全体の成果につなげる
人材育成の目的は、「弱点をなくす」ことだけではありません。
むしろ、「強みを最大限に活かす」ことの方が、本人にとっても組織にとっても、はるかに大きな成果を生み出します。
人は誰しも得意なこと、苦手なことがあります。
苦手なことを平均レベルに引き上げる努力よりも、得意なことをトップレベルに磨き上げる方が、本人のやりがいもパフォーマンスも格段に向上します。
組織の役割は、アセスメントツールなどを活用して個人の強みを客観的に把握し、その強みが最も活かせる役割や目標を設定することです。弱点は、チームメンバーの強みで補い合えば良いのです。
一人ひとりの強みをパズルのピースのように組み合わせることで、個人では成し得ない、強力な組織力を発揮することができるようになります。
人材育成・組織改革なら「村上経営研究所」へ
ここまで、中小企業における人材育成の成功の鍵を握る「目標設定」について、その重要性から具体的な立て方、そして組織で機能させるための仕組みづくりまでを解説してきました。
社員の成長を促し、組織力を高めるためには、戦略的な目標設定が不可欠であるとご理解いただけたことと存じます。しかし、いざ自社でこれを実践しようとすると、
- 「自社の現状に合わせて、どのような目標を設定すれば良いのか分からない」
- 「目標管理制度を導入したいが、何から手をつければ良いか…」
- 「育成の仕組みは作っても、現場で形骸化してしまわないか不安だ」
といった新たな壁に直面することも少なくありません。
人材育成は、一朝一夕に成果が出るものではなく、企業の未来を創るための長期的な投資です。
だからこそ、その第一歩となる設計図は、専門的な知見に基づいて、慎重に、かつ戦略的に描く必要があります。
もし貴社が、本気で人材育成と組織改革に取り組みたいとお考えなら、一度、私たち「村上経営研究所」にご相談ください。
私たちは、これまで数多くの中小企業の組織課題と向き合い、それぞれの企業文化や事業フェーズに最適化された人材育成の仕組みづくりを支援してまいりました。
貴社の課題を深くヒアリングし、社員一人ひとりが輝き、組織全体が力強く成長していくための、具体的なロードマップをご提案します。
【LINE公式アカウントへ】
「いきなり問い合わせるのは少しハードルが高い…」
「まずは、もっと手軽に情報収集から始めたい」
そうお考えの経営者様のために、私たちはLINE公式アカウントをご用意しております。
今すぐご登録いただくと、明日からの人材育成に役立つ、以下の限定特典を無料でプレゼントいたします。
【LINE登録者様 限定特典】
- 社員が辞めない会社をつくる人間力経営・実践チェックリスト5選
- 管理職育成を阻む“3つの壁”チェックシート
- AI音声耳学問
情報収集だけでも大歓迎です。無理な営業は一切行いませんので、どうぞお気軽にご登録ください。



ピンバック: 株式会社村上経営研究所 - 「人材育成研修が成果につながらない…」を解決!中小企業の研修設計・定着のコツ